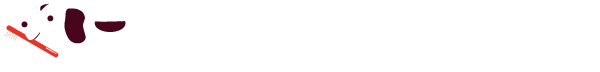- 診査(問診、X線撮影など):金属アレルギーの可能性があるかの見極め
- パッチテスト、血液検査(皮膚科):アレルゲンの特定
- 金属成分分析検査:アレルゲンの存在場所の特定(大学歯学部附属病院での口腔内成分分析 電子線マイクロアナライザEP MA、蛍光X線元素分析法XRFなど)
- 診断:治療計画の立案
- 原因金属の撤去、仮封、テンポラリークラウンの制作など
- 再修復治療:アレルゲンを含まない材料を使用
- 経過観察:アフターケア
大学病院でのデータによると、原因除去療法が終了して2ヶ月経過後では50%以上の患者さんに症状の変化は見られませんでしたが、アレルゲン除去から約2年後で改善傾向は約60%に増えているそうです。しかし、中には症状の変化は見られなかった人もいますので、修復物を外したからといって必ず治るとは限りません。
歯科用の金属は用途に応じて、硬さや引っ張り強さの理工学的性質、加工のしやすさ、生体親和性、耐腐食性、経済性などを求められるため、数種類の金属をミックスして合金で作られます。